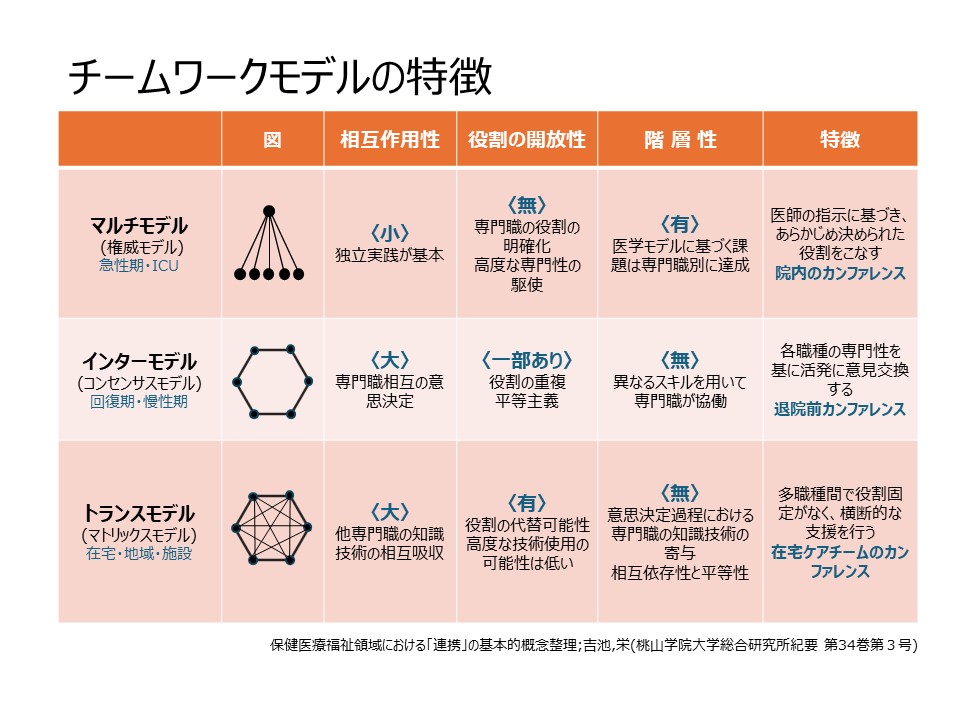令和7年2月26日に北見市が開催した「令和6年度 医療機関・在宅ケアマネジャー連携会議」にて「身寄りなし患者の支援課題について」をテーマとしたグループワークを当センターが担当した。参加者は医療機関の入退院支援担当者と居宅ケアマネジャーである。
そもそも今回、なぜこのテーマにしたのか。これは以下のレポートを読み、非常に危機意識を私が感じたからであった。(以下レポート要旨)
- 福祉サービスの利用を必要とするような困難がなく生きてきた人が、高齢期になってはじめて「身近で手助けする人がいない課題」に直面するケースが、今後は増えると予測される。
- とくに独居高齢男性を中心として、いざとなれば(日常的な付き合いを前提としないで済む)行政に頼りたいという意向を持つ傾向があるが、現段階では行政が個人の生活状況を把握して支援を提供する仕組みが十分にあるわけではなく、問題が大きくなって初めて周囲がその解決をはからざるを得ないのが現実である。
- また、自治体の小規模化や若年人口の減少を踏まえると、従来の行政サービスによって、増えていく支援対象をカバーすることは相当に困難と考えられる。社会的に、何らかの新たな解決策を見出すことが急務である。
人口減社会は個人を取り巻く地域や世帯・家族の縮小をもたらすばかりでなく、高齢期の暮らしへの影響、特に健康や介護の問題が顕在化して初めて「身近で手助けする人がいない課題」に直面することに気付いたからである。現に身寄りなしで困っている方はもとより、今現在は自分自身で身の回りをことができる方であっても、将来へ向けたの支援体制を整えておかなければならない。私の仕事はこれまで医療と介護の課題を取り扱ってきたけれど、この課題は将来生まれる社会課題として直ちに取り組まなければならないテーマだと感じた。
身近で手助けする人がいない場合、医療機関においては自宅退院への選択の可能性は小さくなる。また護保険サービス契約も怪しくなる。これまで「身近で手助けする人」の存在を前提としてきたサービスの大転換が求められる。
話しを連携会議へ戻します。
連携会議で「身寄りなし患者の支援課題」を協議するにあたり、居宅ケアマネジャーを対象に身寄りのない方の入退院支援に関わる調査を行った。調査にあたり必要なことは身寄りのない方の定義だ。そこで、㈱日本総合研究所が「介護職員等における身寄りのない高齢者等に対する支援の実態に対する調査研究事業(令和6年度 老健事業)」で用いた以下の定義を活用して調査をおこなった。
身寄りのない方とは、緊急連絡先となるような親族が存在しない方。親族はいるが疎遠や高齢等の理由で日常的に支援を受けることが難しい方を指す。重大な出来事(入院時や死亡時)のみ親族が対応するが日常的な支援を受けることが難しい場合も身寄りのない方として考える。
調査では北見市の居宅ケアマネジャー約200人のうち55人(回答率 27.9%)から回答を得た。調査結果をまとめると以下のことが判明した。
- 全ケース1,543ケース数中、身寄りなしの方がいると回答のあったケースは108(6.9%)で、将来の身寄りなしを含めると179ケース(10.9%)となり、要介護ケースの約1割であった。
- 要介護ケースにおける単身世帯率は37.0%で、高齢者夫婦世帯は59.0%であった。
- 要介護ケースにおける成年後見制度の利用率は14.8%であった。
- ケアマネジャーの法定外業務としていつもある(月1回)程度の内容は、郵便・宅配、書類作成の代行や発送であった。
- 法定外業務への対応は事業所の業務が無償で実施していた。
- 支援が難しい人への支援の際、助けになるのは、併設する事業所や同僚であった。
- 入院時に保証人・緊急連絡先等を求められる医療機関が多いとケアマネジャーが回答した。
- 身寄りのない方が介護保険サービスを利用できるようするために、必要だと思われることで最も多かったのは「医療機関や施設が保証人がいなくても入院、入所を受け入れてくれること」であった。
- 身寄りのない方の支援に対し「大きな負担感がある」と回答したケアマネジャーが約7割いた。
以上の結果から「身近で手助けする人がいない課題」に直面している方は非一定数いることが判明した。
医療機関とケアマネジャーの入退院支援に関する会議ということもあり、話題はケアマネジャーの業務負担をどう解消していくかという課題もあった。これはこれで解決をしていくとして、グループワークを終え「身近で手助けする人がいない課題」の解決へは今後、以下の手順でを進めることが必要だと感じる。
現状と課題の把握
「身近で手助けする人がいない課題」は各機関(行政・医療機関・介護サービス・その他)でどのように発生しているか、またどの程度に人数がいるか。
現在行われている支援
上記の課題を各機関(行政・医療機関・介護サービス・その他)はどのように対処しているか。今後対象者が増加した場合に持続可能かどうか。
今後立案すべき支援や対策
現に「身近で手助けする人がいない課題」に直面している方に対する対策は何か。
どういった団体を構成した協議体(既存の団体を含む)でで検討していくか。
将来の「身近で手助けする人がいない」予備軍の方に対し、現在取り組めることは何か。
また、この課題に取り組んでいる地域同士の情報交換も必要だと感じる。この課題はみなに関係するが、どこが主体的に扱うかが定まっておらす、その結果誰も取り扱わずただ見過ごされてしまう。
今後はこの身寄りのない方が抱える課題を地域全体の課題として各地域で取り組んでいくことが望まれる。